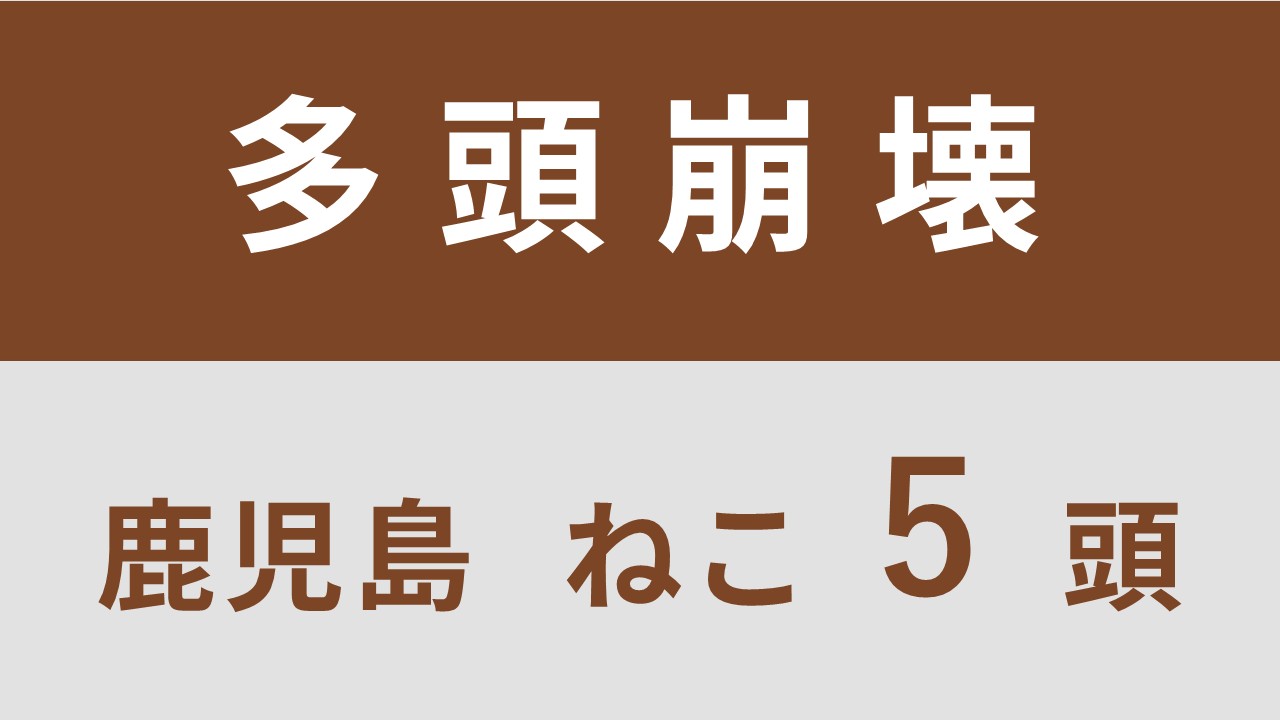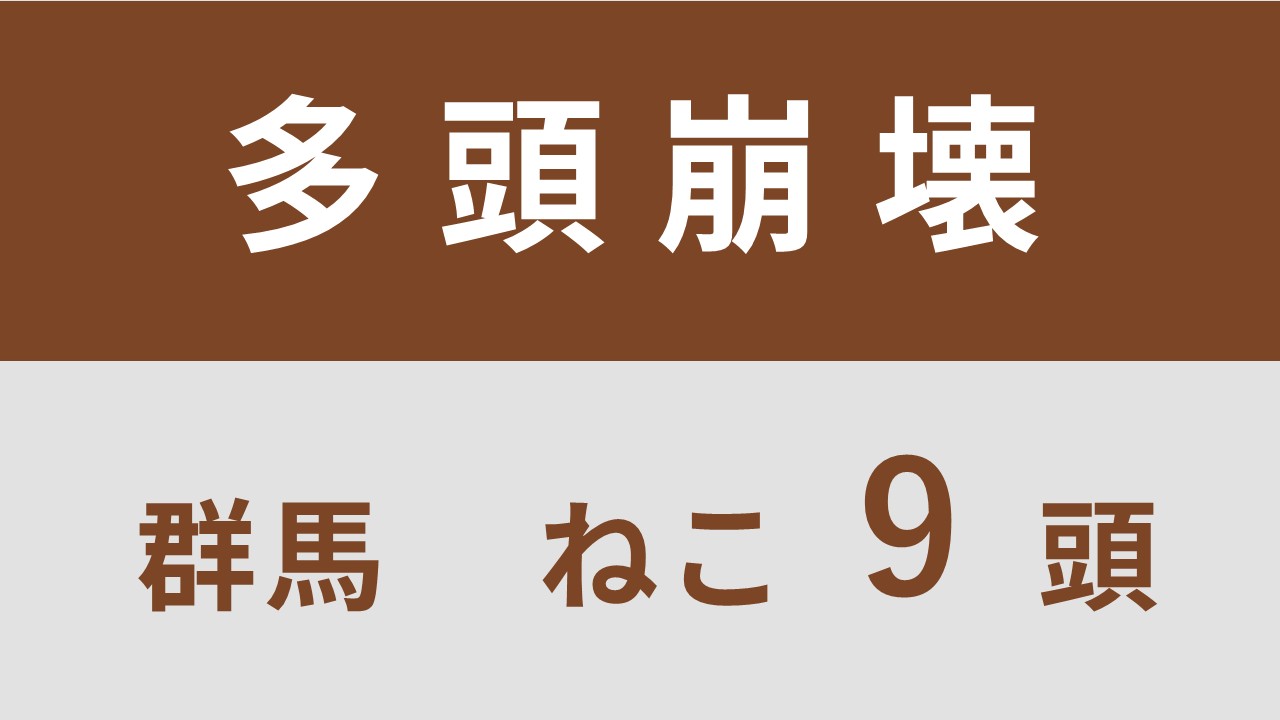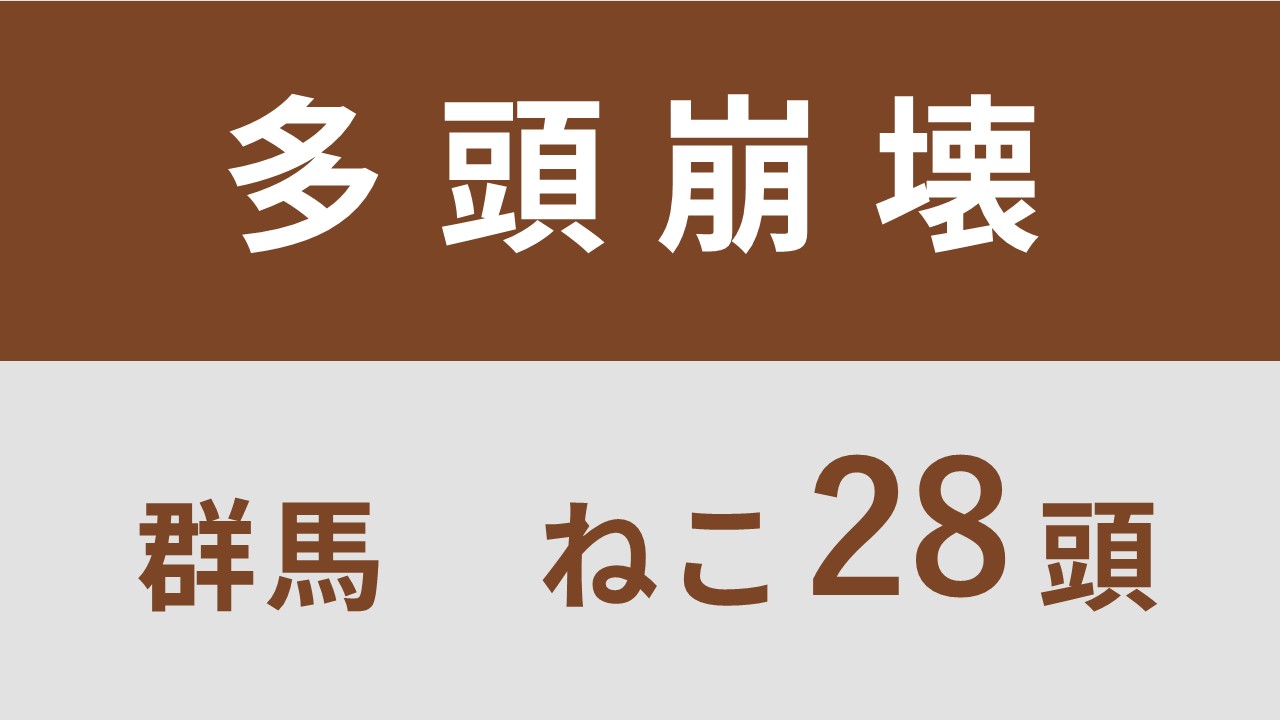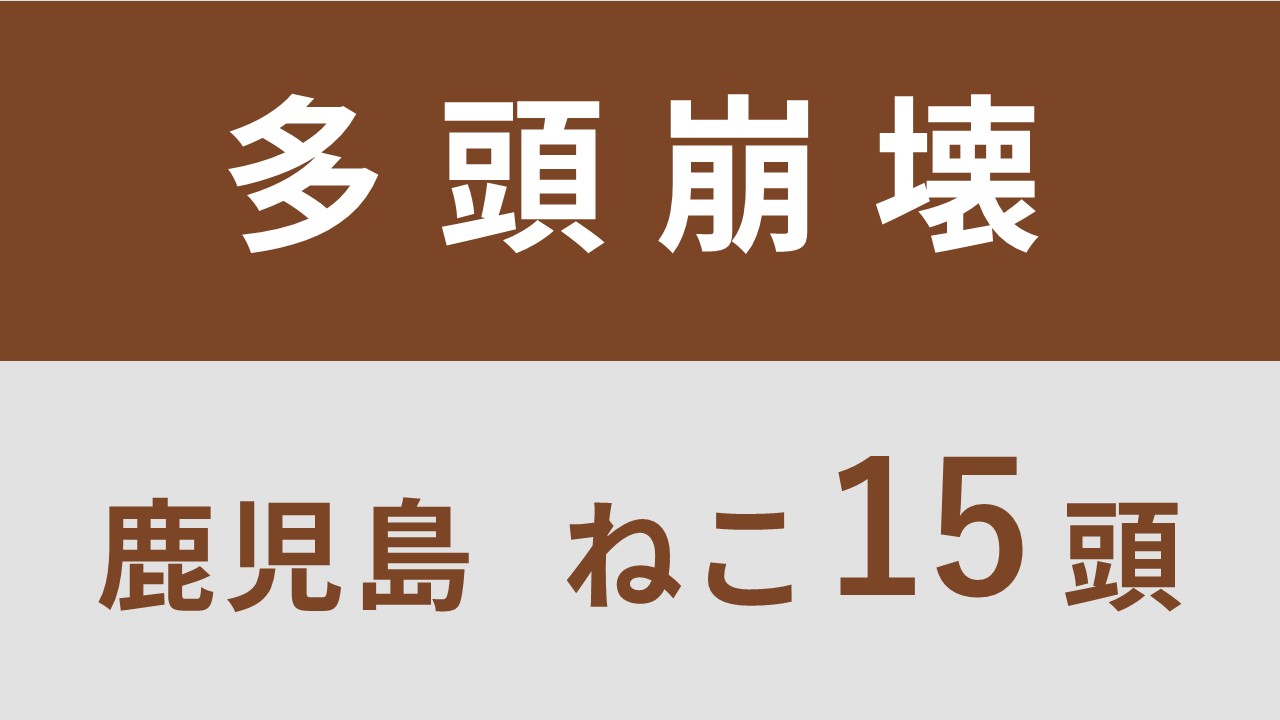5_北海道美幌町多頭飼育救済支援レポート(行政枠)
申請No.5
申請日:2025年4月7日
申請/美幌町 建設部 環境管理課
場所:北海道網走郡美幌町
居住者:当事者本人(71歳、男、無職)
居住環境:持ち家/一戸建て
生活保護の受給状況:受給していない
多頭飼育現場の猫の総数(うち子猫の頭数):70頭(0頭)(69頭で申請したが、実際は70頭であった)
手術日:5月11日、12日、13日、6月1日
協力病院:Mobile VET Office
チケット発行数:69枚
手術頭数:58頭(保護された4頭、支援前に手術を行った4頭、捕獲できなかった4頭の計12頭を除く)
協働ボランティア:非営利型一般社団法人 オホーツクねこの会
申請から不妊手術完了までの経緯(報告書より)
- 6~7年ほど前に野良猫1頭を保護。最初はこの1頭のみであった。
- 他の野良猫への餌やりを始め、その猫たちを自宅内に保護していき増加。さらに子猫が生まれるなどして現在の頭数に至る。
- 近隣住民からの苦情により発覚。最初は2020年、多頭飼育崩壊ではなく野良猫への餌付けに関して注意し、2021年にも同様の内容で注意を行っている。2024年5月になって、近隣住民から糞尿被害と臭いの苦情が寄せられたことで多頭飼育崩壊が起こっていることを確認した。
- 2024年5月にオホーツク総合振興局職員とともに当事者宅を訪問し、自宅内の様子を確認するため立ち入りを依頼するも「片付いておらず見せられない」との返答。1か月後に再訪することとし、まずはこれ以上増えないよう不妊手術を進めるよう伝える(この時点で30頭)。
- 同年7月、オホーツク総合振興局職員とともに再訪するも不在。近隣住民から当事者が急病により救急搬送されたと聞き、近所に居住している当事者の弟を訪問。当事者入院中の餌やり等を依頼し、弟の許可を得て自宅内に入ったところ、猫の糞尿が散乱して悪臭がしていた。猫は目視で40頭前後確認できたが、状態は良く病気や栄養失調等はない様子であった。
- 同年7月に当事者が退院。自宅を再度訪問し、今回の救急搬送の件もあることから早急に不妊手術を行い譲渡を行うことを指導した。再入院の予定があったことから、まずは頭数の確認作業を行うよう依頼。同年9月に頭数確認を完了し、動物病院へ手術を依頼した。
- 当事者から手術費用の負担可能との回答を得て、同年10月に不妊手術を予定していたが、体調不良により入院や検査等が続いて費用が払えない様子であった。当事者の弟に金銭援助を打診するも厳しい状況で、当事者から来年の夏までに費用をためると申し出があったことから様子を見ることにした。
- しかし、2025年3月にオホーツク総合振興局職員が訪問した際に貯金ができていないことが判明。その後も改善が見られないことから、多頭飼育救済支援の申請を決定した。
- 猫の頭数と協力病院までの距離(300km以上)から搬送が困難として往診を希望。審査の結果、協力病院の了承を得て「往診」での対応となった。
- 当初、69頭で申請していたが実際には70頭であった。ボランティア団体が保護した5頭(このうち1頭は特別な事情により保護後にチケットを使用して手術が実施された)、妊娠が判明してチケット発行前に不妊手術を行った4頭、支援期間中に捕獲できなかった4頭の計13頭を除く58頭が手術済みとなった。
- 70頭のうち38頭(未手術4頭を含む)がボランティア団体に引き取られ、当事者宅には32頭(未手術4頭含む)が残る。
- 清掃により飼養環境が大きく改善されたこと、飼育頭数が減ったことから、猫の健康状態は維持できておりストレスも軽減された。申請時からトイレの数を4倍に増やし、スペースも広がっている。
- 捕獲できなかった4頭については、捕獲作業を継続し、捕獲できた場合はボランティア団体に引き渡す予定である。この4頭とボランティア団体が保護したうちの未手術の4頭については、保護先や譲渡先で不妊手術を行うよう行政からの指導を依頼済み。
- 今後もボランティア団体を通じて譲渡先を探し、譲渡が決まって保護頭数に空きが出た時点で当事者宅から引き取る予定。最終的には全頭の譲渡を目指すが、それまでは当事者と猫32頭は同じ場所に住み続ける。
| 手術日 | オス | メス | 耳カットのみ | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 5月11日 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 5月12日 | 25 | 7 | 0 | 32 |
| 5月13日 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 6月1日 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | 36 | 22 | 0 | 58 |
【現場写真(支援前)】


今回の取り組みを振り返り、改善すべき点や今後の配慮事項(報告書より)
ボランティア団体と協働し、多頭飼育崩壊となっていた現場の環境改善を図ることができた。今後は、こうした状況を生まないよう、対策を図っていきたい。
どうぶつ基金スタッフコメント
まず最初に、往診にご協力いただいた「Mobile VET Office」様に感謝申し上げます。
多頭飼育崩壊の解決において「様子を見る」という選択肢はありません。なぜなら様子を見ている間に、さらに猫の数が増えるからです。本件においても、2024年7月の時点で目視できたのは40頭前後、当事者の資金準備を待つ間にどんどん頭数は増え、結局資金は用意できず、申請時にはほぼ倍の70頭になっていました。40頭の時点で当事者自らが費用を負担して解決することは不可能に近いと考えます。この時点で手術できていれば、不幸な環境に生まれてくる命を減らせたのにと、とても残念です。
70頭もの多頭飼育救済に対応された行政職員の皆様、ボランティアの皆様も大変なご苦労であったとお察しいたします。多頭飼育崩壊の解決において最も重要なことは、不妊手術を「すぐやる・全部やる」です。4頭の未手術の猫がいれば、1年後には元通りになってもおかしくありません。未手術の猫4頭を一刻も早く捕獲・ボランティア団体へ引き渡しを行い、今後この現場から決して猫が増えることがないよう、今回の苦労が繰り返されないよう、作業の継続と定期的な確認をぜひとも行っていただきたいと強く願います。