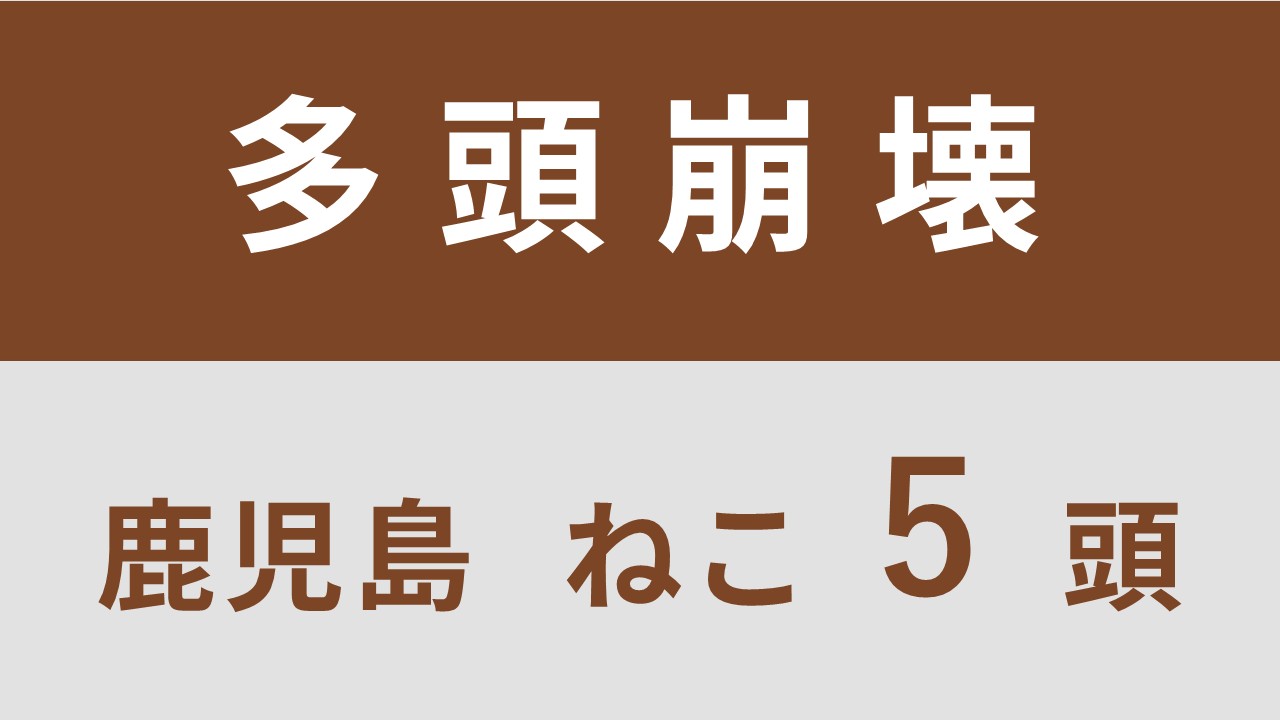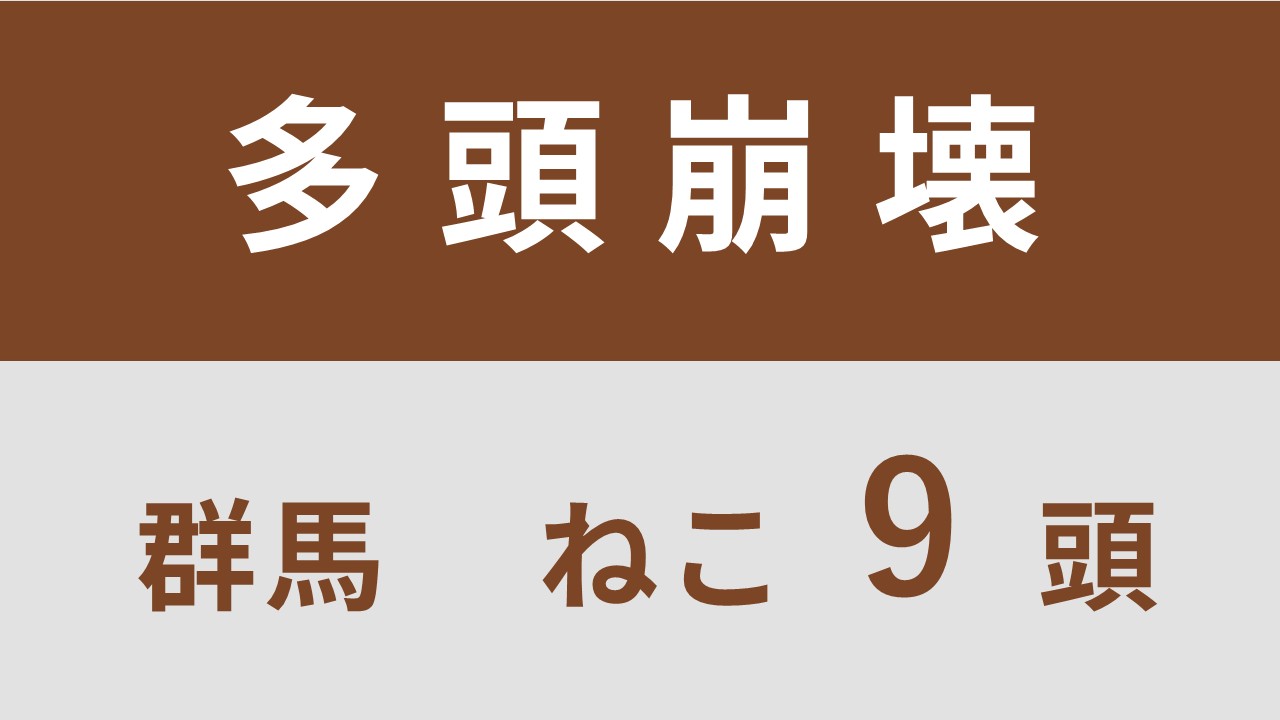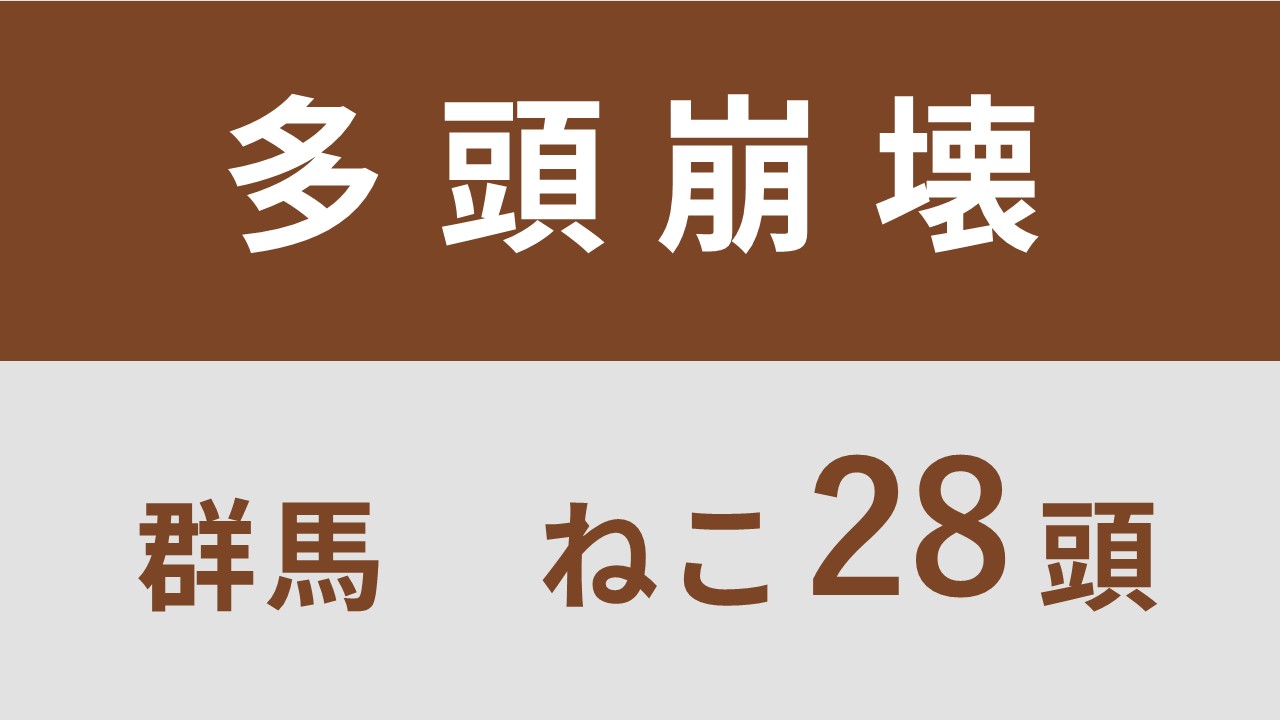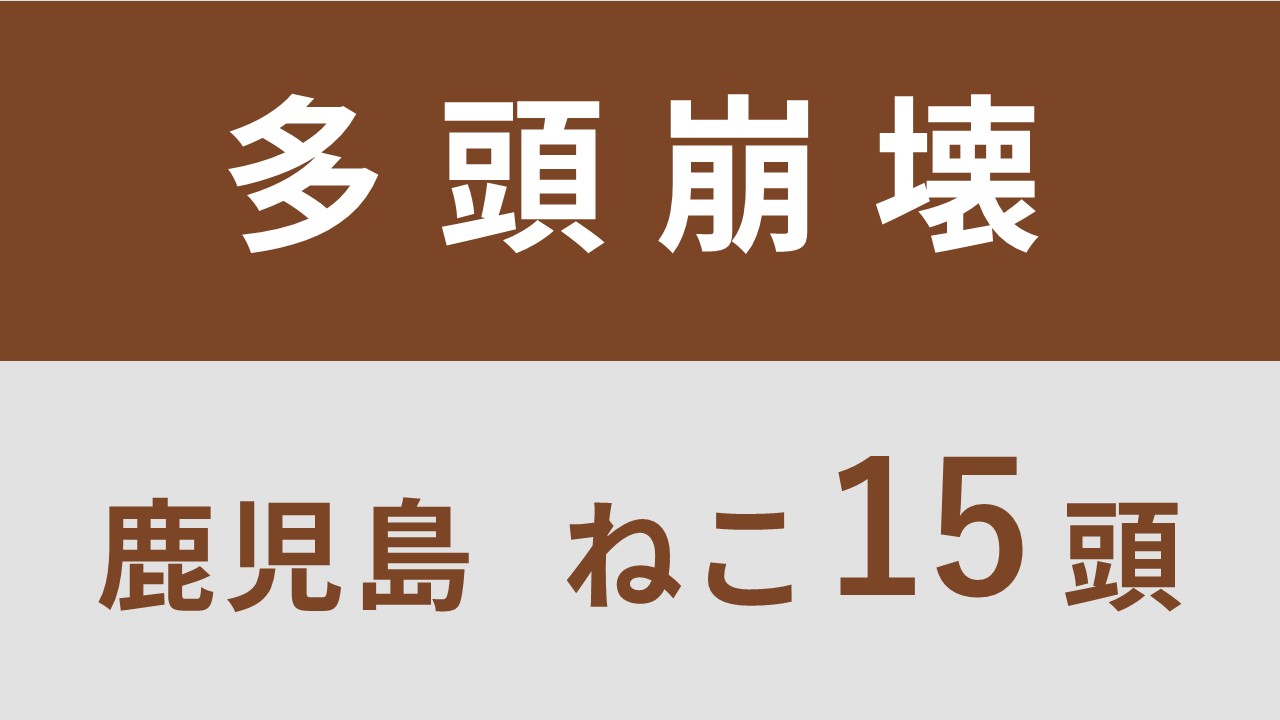42_北海道むかわ町多頭飼育救済レポート(行政枠)
申請No.42
申請日:2024年11月19日
申請/実施責任者:むかわ町 企画町民課
場所:北海道勇払郡むかわ町
居住者:当事者本人(21歳、女 無職)母(45歳、パート)兄(22歳、無職)祖父(75歳、農業)子(2歳、現在別居)
居住環境:①当事者宅(持ち家/一戸建て)②当事者の母宅((団地・集合住宅/賃貸)
生活保護の受給状況:受給していない
多頭飼育現場の猫の総数(うち子猫の頭数):52頭(13頭)(当初40頭で申請するも実際は52頭であった)
手術日:1月30日、1月31日
協力病院:Mobile VET Office
チケット発行数:40枚
手術頭数:40頭
協働ボランティア:なし
申請から不妊手術完了までの経緯(報告書より)
- 当事者の母が物心ついた頃(40年ほど前)にはすでに家①に十数頭の猫がいた。20年ほど前、当事者、母、兄が家①にいた猫を2頭連れて家②に移った。
- 家①の十数頭の猫が妊娠・出産、また、敷地内に猫を捨てられることもあって頭数が徐々に増えた。担当者が確認した段階で24頭を確認、うち4頭は室内飼育であった。
- 家①で増えた猫のうち、病気で保護が必要な猫や群れのなかでいじめられる猫を家②に運んで飼育しており、こちらは20〜30頭を室内飼育している。家①で屋外飼育している猫を家②に運び込むことが多々あり、現在は家②の方が飼育頭数は多い。当事者と母の適切飼育について自覚や理解が低かったことから頭数が増えていった。
- 当事者の子は事情により現在別居となっており、児童相談所や他部署(保健師担当部署)から当事者宅が多頭飼育の状況にあると報告があり発覚。
- 居住面積に対して猫の頭数が多く、大多数の猫は酷い目ヤニで病気の可能性がある。目ヤニについては当事者と母から風邪をひいていると回答があったが、頭数が多すぎることで不衛生な状況になっており、猫にとっても家族(特に今後同居する可能性のある児童)にとっても良くない状況であることを説明。この時点で居住地2件に計50頭の猫がおり、殺処分等の措置を避けるためにも、猫の頭数がこれ以上増えないよう不妊手術をすること、譲渡先を探す必要があることを指導した。
- 不妊手術については同意したものの、当事者は譲渡先探しに後ろ向きであった。特に保健所を経由した譲渡先探しに対して拒否感が強く、それ以外の方法であれば検討したいとのこと。50頭のうち子猫10頭について、当事者自身のつてで里親が見つかり引き取ってもらえた経緯があるためと思われる。
- 今後、当事者の子が同居する可能性があり、現在の居住環境はその子にとっても猫にとっても悪く改善の見込みがない。当事者および当事者家族は、金銭的にも理解・行動面からも解決する力がないと判断し、多頭飼育救済支援の申請を決定した。
- 頭数が40頭と多いことから一度に搬送することが難しく、行政職員が猫の運搬・移送に慣れていないことから、猫のケガや逸走等の不安があった。また、少ない日数(可能であれば1日)で不妊手術を完了したいことから往診希望で申請を行い承諾を得た。
- 40頭で申請していたが、当事者が失念していた1頭と申請後に生まれた子猫11頭がおり、実施時は52頭であった。チケットを使用して40頭の不妊手術が完了。1頭は獣医師の判断による手術不可となり今後も手術予定はない。子猫11頭については里親が見つかり、手術可能な時期に里親にて不妊手術を行う予定である。
- 新たに飼い主のいない猫2頭も発見されたが、この2頭については支援団体により不妊手術を完了した。
- 支援後は猫をグループで分けるようにし、トイレと餌場の数を増やしたことから猫のストレスも若干軽減されている。トイレの清掃は行っているが、頭数の多さからアンモニア臭はあり、支援前と比較して改善はされているがまだ不衛生な状況である。
- 41頭の猫は引き続き当事者が飼養を継続するが、里親探しを継続し、当事者のもとには8頭程度を残す予定である。
| 手術日 | オス | メス | 耳カットのみ | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1月30日 | 16 | 10 | 0 | 26 |
| 1月31日 | 3 | 11 | 0 | 14 |
| 計 | 19 | 21 | 0 | 40 |
【現場写真(支援前)】

【現場写真(支援後)】

今回の取り組みを振り返り、改善すべき点や今後の配慮事項(報告書より)
どうぶつ基金と協力病院のおかげで、不妊手術については無事に完了することができたが、当事者の意識は未だ低いままである。多頭飼育崩壊している状況でも問題意識を持てていない状況であり、里親探しについても「できることなら出したくない」という発言も聞かれる。
多頭飼育救済について、当事者にもう少し理解していただける進め方ができればよかったと感じている。
終了後も当事者に働きかけは行っているものの、どうぶつ基金への報告が遅れ迷惑をかけてしまった点も反省点である。
どうぶつ基金スタッフコメント
まずは、往診での手術に応じてくださった「Mobile VET Office」様に感謝申し上げます。本件の場合、日数をかけると当事者が手術を拒否する可能性もあったため、2日間で支援を完了できたことは本当に良かったと思います。
当事者は猫への執着が強く、猫を手放すことについて納得していないようです。不妊手術をせず、劣悪な環境で猫を飼育しているにも関わらず、その環境が異常であるとは思っていません。支援後も飼養環境の改善には程遠く、この飼養環境で飼い続けることは「虐待」にあたることを理解いただくには、動物行政を担当する振興局等からの適切な指導が必要です。
多頭飼育崩壊の救済は不妊手術を終えたら完了、というわけにはいきません。特に今回のような当事者の場合、難しい面はありますが、定期的に関わりを持ち続けることが必要です。飼養環境の改善を促し、里親探しを継続し、本当に飼育頭数が8頭程度になるまで、行政にはあきらめずに向き合っていただきたいと思います。