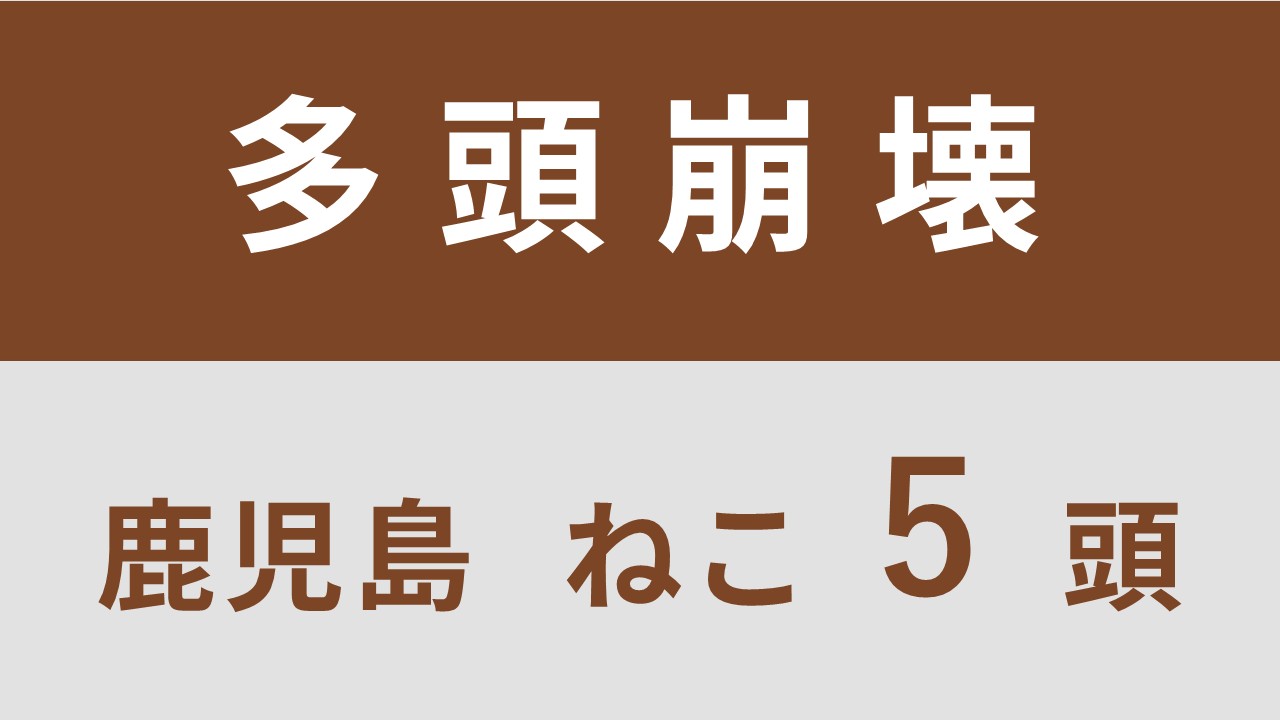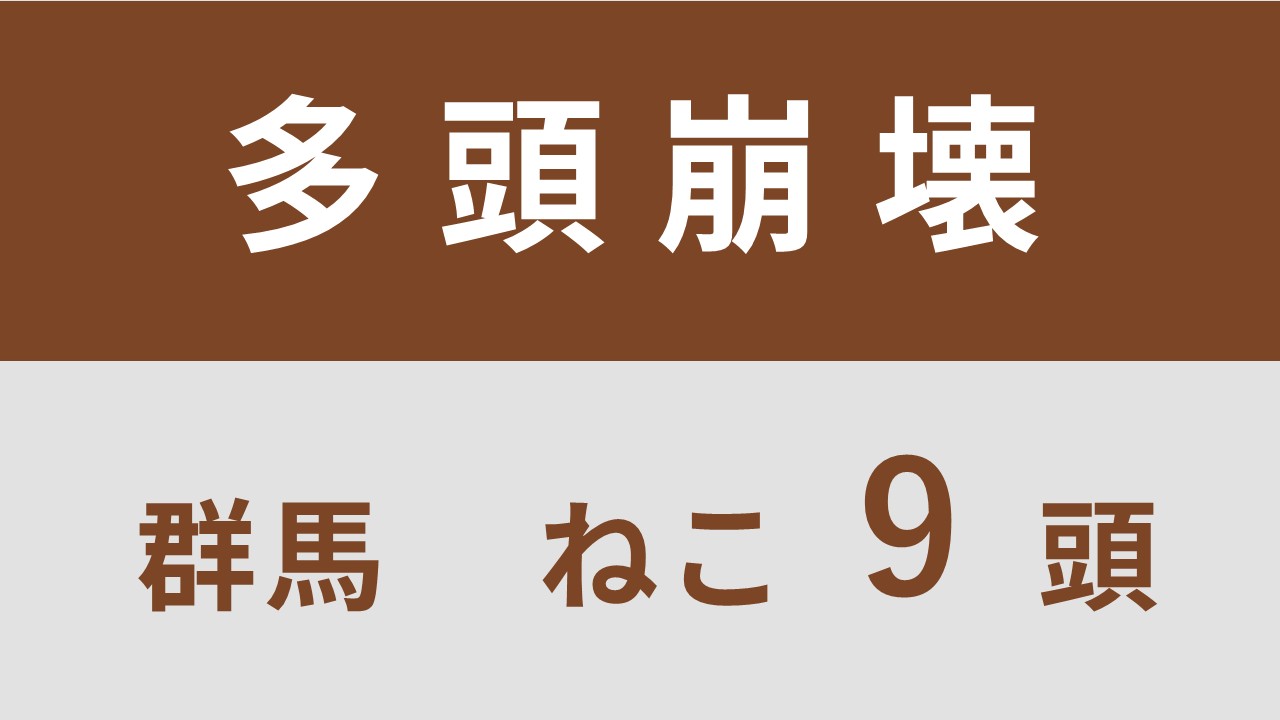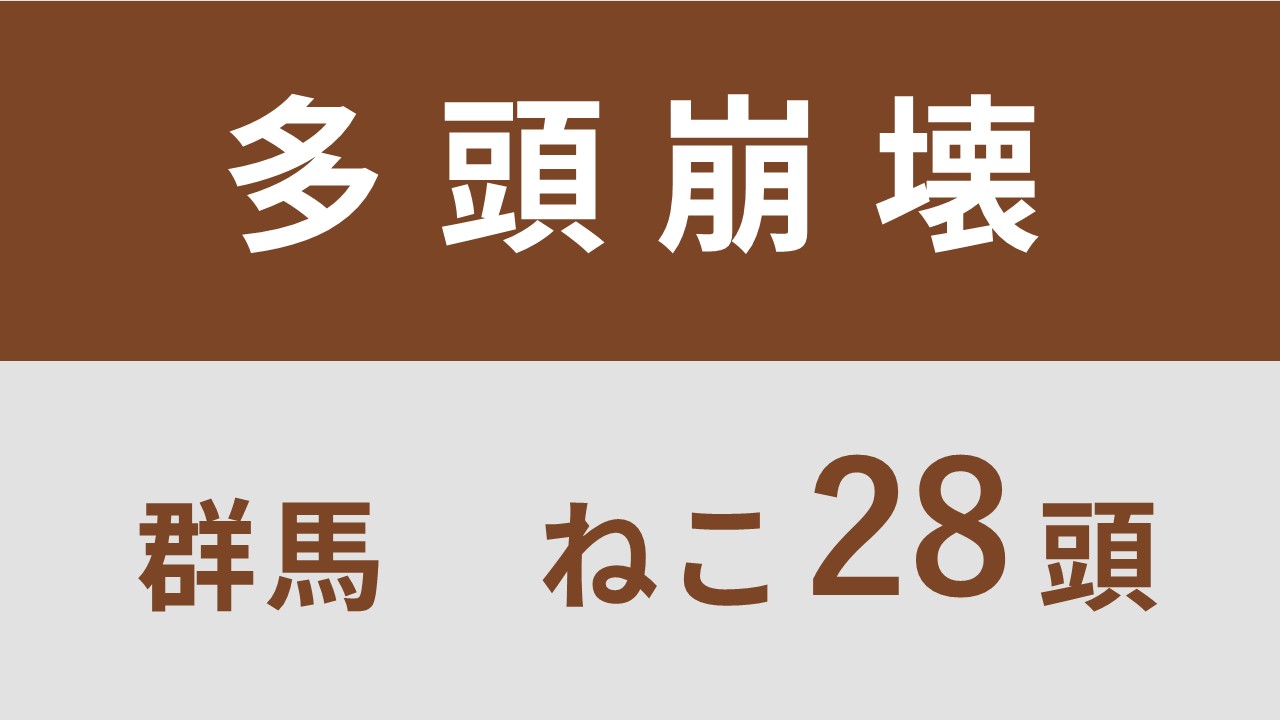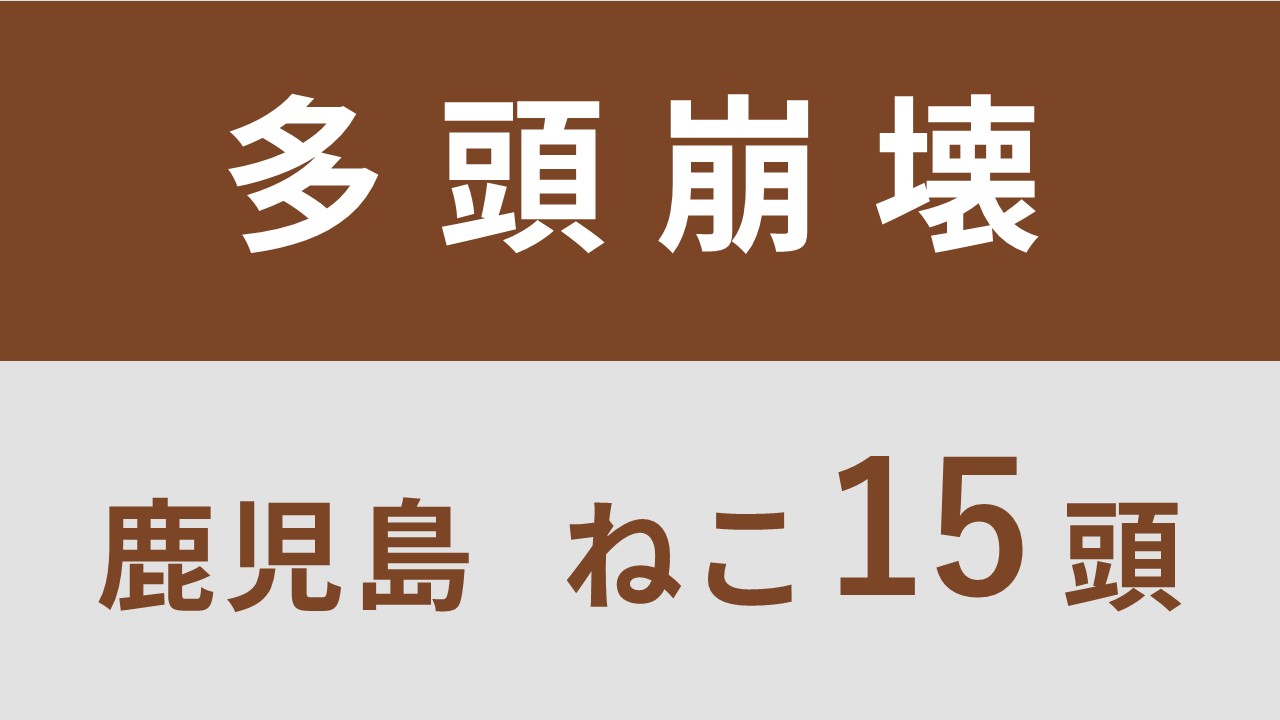48_和歌山県高野町役場多頭飼育救済レポート(行政枠)
申請No.48
申請日:2024年12月20日
申請/実施責任者:高野町役場 環境課
場所:和歌山県伊都郡高野町
居住者:当事者本人(77歳 女 無職)、配偶者(77歳 無職)
居住環境:持ち家/一戸建て
生活保護の受給状況:受給していない
多頭飼育現場の猫の総数(うち子猫の頭数):35頭(10頭)
手術日:2月19日、2月20日
協力病院:北摂TNRサポート のら猫さんの手術室
チケット発行数:30枚(手術済み5頭を除く30頭分を申請)
手術頭数:30頭
協働ボランティア:はしもとさくら猫の会 和歌にゃんず
申請から不妊手術完了までの経緯(報告書より)
- 2012年頃、家の近くで捨てられていた猫3頭を飼い始めた。
- 費用が高額で、一度に3頭の不妊手術ができずオス1頭のみ去勢手術を行った。手術できなかったメス2頭が妊娠し、飼い始めてからの数年であっというまに頭数が増えた。
- 当事者宅の猫に関する苦情が寄せられたボランティア団体から役場に連絡が入り、ボランティア団体の協力によって当事者宅を訪問。聞き取り調査を行い多頭飼育であることが発覚した。
- 当事者夫婦は高齢で入院していた時期もあり、杖を突くなど歩行も不安定である。また、聞き取り調査において「病気や車にはねられるなどして何頭も亡くなっていくことが辛くてたまらない。今後のことを考えると不安でいっぱい。何年も暗闇の中でいるようだ」「不妊手術も少しずつ行っていたが、費用が高額で一度に手術できない間に猫が増えてしまった」との話があった。以上のことから、当事者ではどうすることもできない状態にあると判断し、申請に至る。
- 支援を進めるにあたり、ボランティア団体が訪問して猫の栄養不良や猫風邪の症状を確認。当事者に手術前に猫の体調を整える必要があることを伝えた。また、支援物資として、ボランティア団体から総合栄養食、子猫用フード、猫風邪に対する点眼、点鼻薬、電気マット、毛布が提供され、点眼と点鼻薬については使い方を指導した。
- すでに手術済みの5頭を除く30頭分のチケットを申請。30頭の手術が無事に完了し、現場の猫は全頭手術済みとなった。
- 当事者の希望により、猫は今後も同じ場所で当事者と暮らす。頭数が多く当事者夫婦も高齢で、飼育管理能力を超えてしまっているため、今後も定期的に訪問して状況を確認するなど支援を続ける。
- どうぶつ基金のアドバイスを受けて、職員とボランティアの協力によりトイレを3個→11個に増設。臭いが軽減し、清掃によって運動スペースも確保され改善された。最終的には猫の数とトイレの数が一致するように継続して支援を行っていく。
- 衛生環境が改善され、猫の健康状態も良くなった。
| 手術日 | オス | メス | 耳カットのみ | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 2月19日 | 6 | 9 | 0 | 15 |
| 2月20日 | 4 | 11 | 0 | 15 |
| 計 | 10 | 20 | 0 | 30 |
【現場写真(支援前)】

【現場写真(支援後)】

今回の取り組みを振り返り、改善すべき点や今後の配慮事項(報告書より)
どうぶつ基金、富貴支所、ボランティア団体、個人ボランティア、当事者などさまざまな方の協力を得て、手探りながらもつつがなく事業を進行することができた。橋本市、かつらぎ町、御所市にも、住民の方へ向けての事業前後の説明資料の提供や事業の進め方についてご協力いただいた。
町としてあまり多くのことができず、現場と距離があることから連携が取り辛い状況だったが、関わってくれた方々の尽力でやり遂げることができた。
反省点としては、①多頭飼育崩壊に気付くのが遅れてしまったこと、②今回の体制で事業を続けることが難しいことが挙げられる。
①については、高野町でも多頭飼育届出制度を導入し、早期に多頭飼育崩壊の兆候をつかむ・早期に多頭飼育崩壊を発見することで、その件数を減少させることができると考えている。②については、今回、富貴支所や橋本市を活動拠点とするボランティアに無理を言って手伝っていただいたことから、高野町内でボランティア活動に参加してくれる地域サポーターの方を募集し、住民と協働で問題へ取り組むことで継続性を確保する必要があると考えている。
現状の業務と折り合いを付けながらにはなるが、反省点を踏まえ必要な施策を実施することで、猫と人が共存できる社会を構築していきたい。
どうぶつ基金スタッフコメント
3頭の捨て猫を拾ってから多頭飼育崩壊に至るまでの経緯を見ると、当事者にも苦悩があったのだろうと推察します。ボランティアや行政とつながったことで今後もサポートが受けられること、また、全頭の不妊手術が完了して猫の繁殖が止まったことに当事者も安堵しているのではないでしょうか。不妊手術が必要であることを理解しながらも、このような結果に至ってしまったことを当事者は誰よりも悔いているはずです。亡くなった猫たちのことが辛いという気持ちがあるなら、引き続きともに暮らす35頭の猫が健やかに穏やかに過ごせるよう、飼い主としての責任を果たしてほしいと思います。
高野町は、多頭飼育崩壊やその予備軍をいかに早く見つけるか、見つけた後はどのように対応していくのか等、今回の支援活動を通して見えてきた課題を次につなげようとしています。その取り組みが住民の意識を変え、実を結ぶことを心から願います。