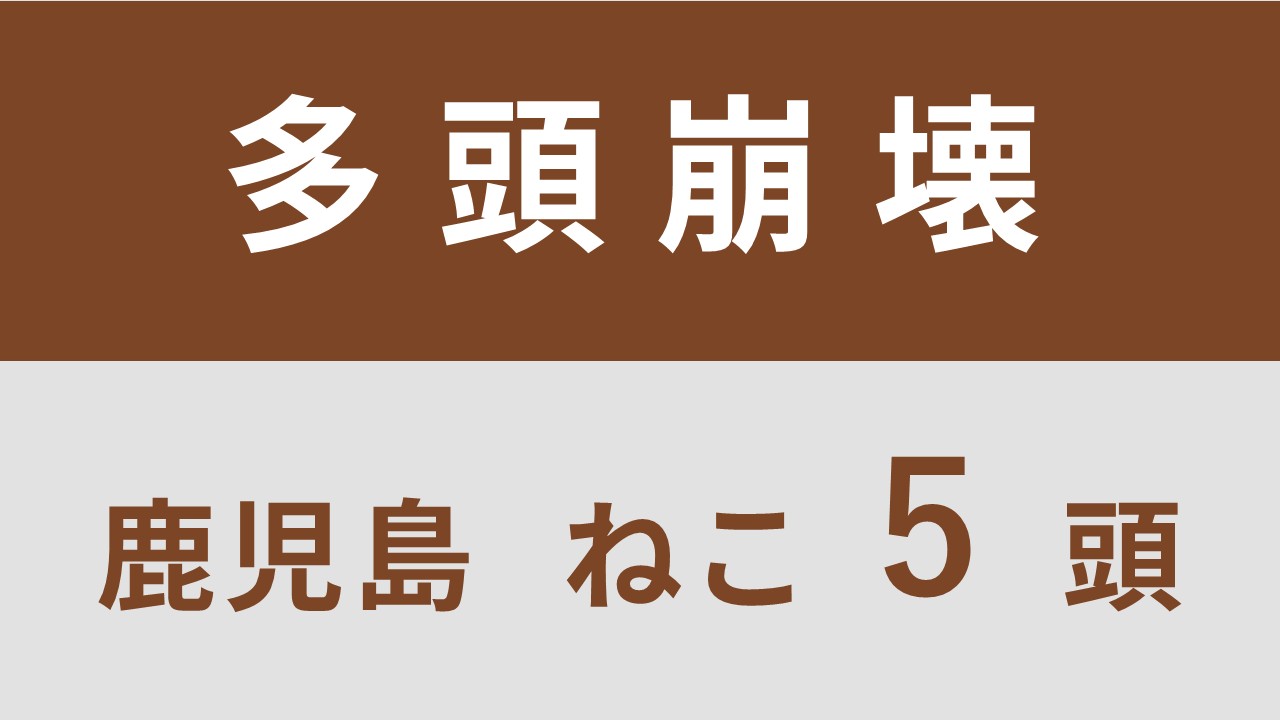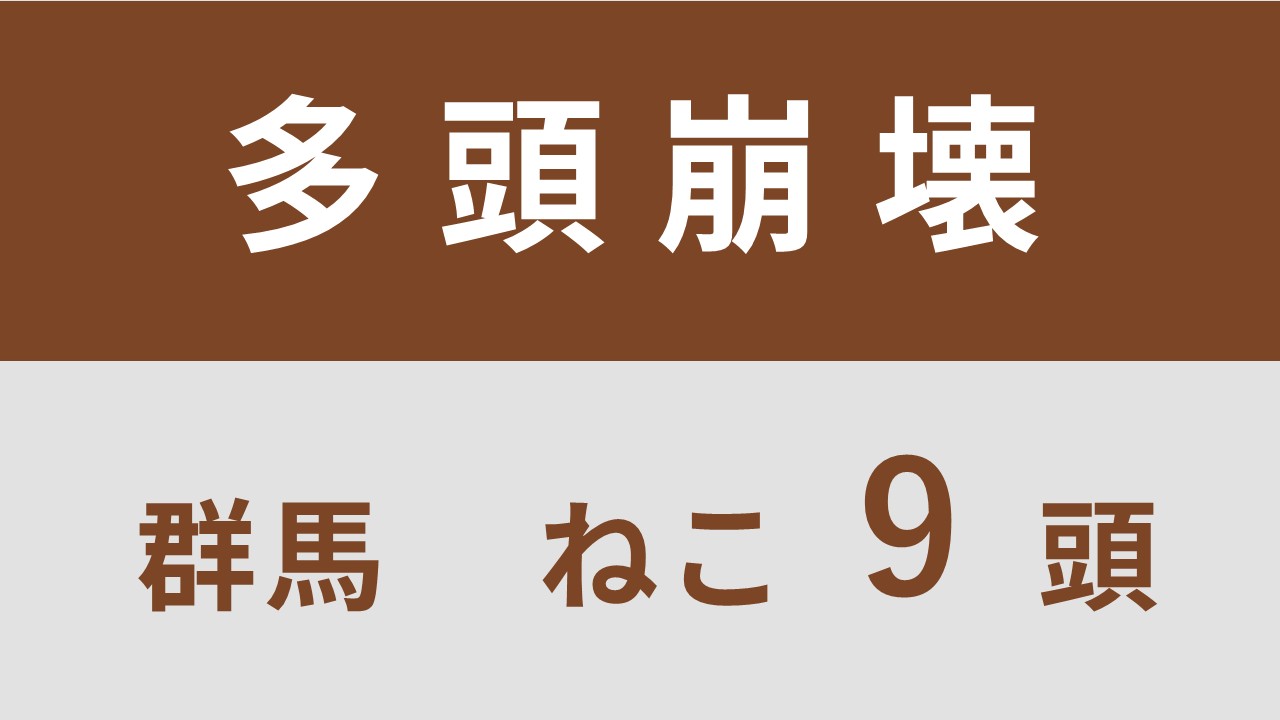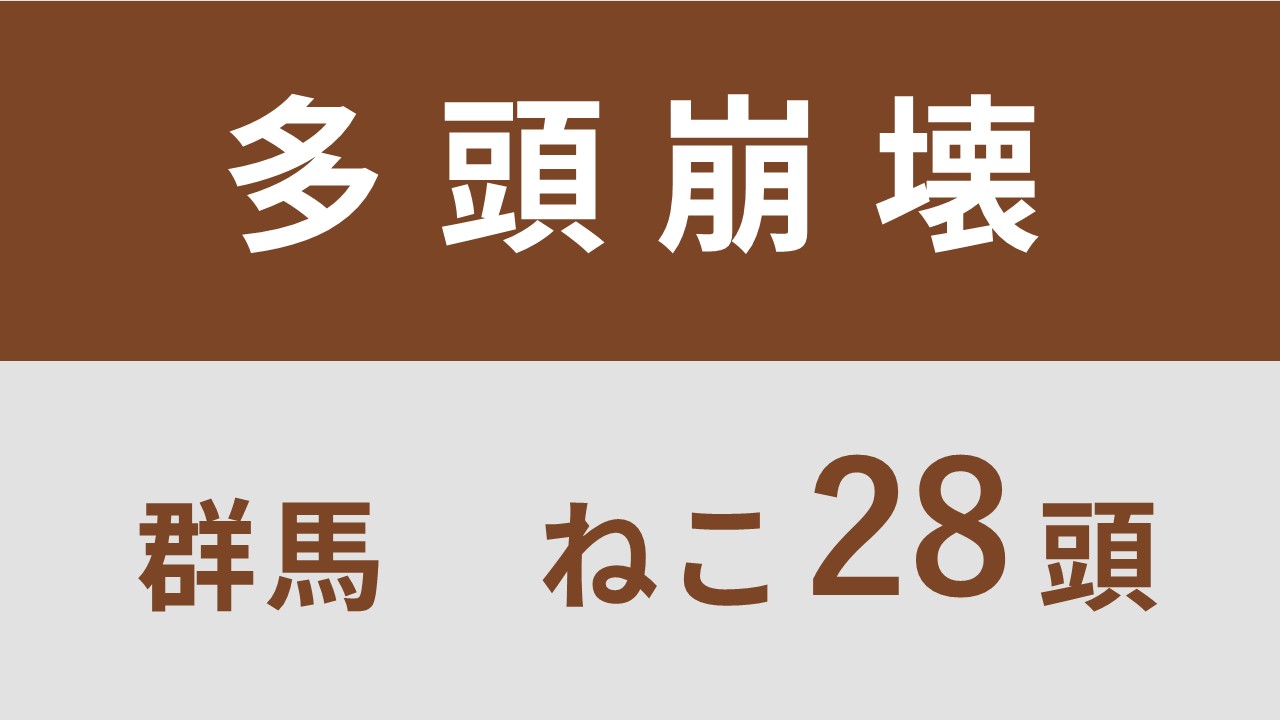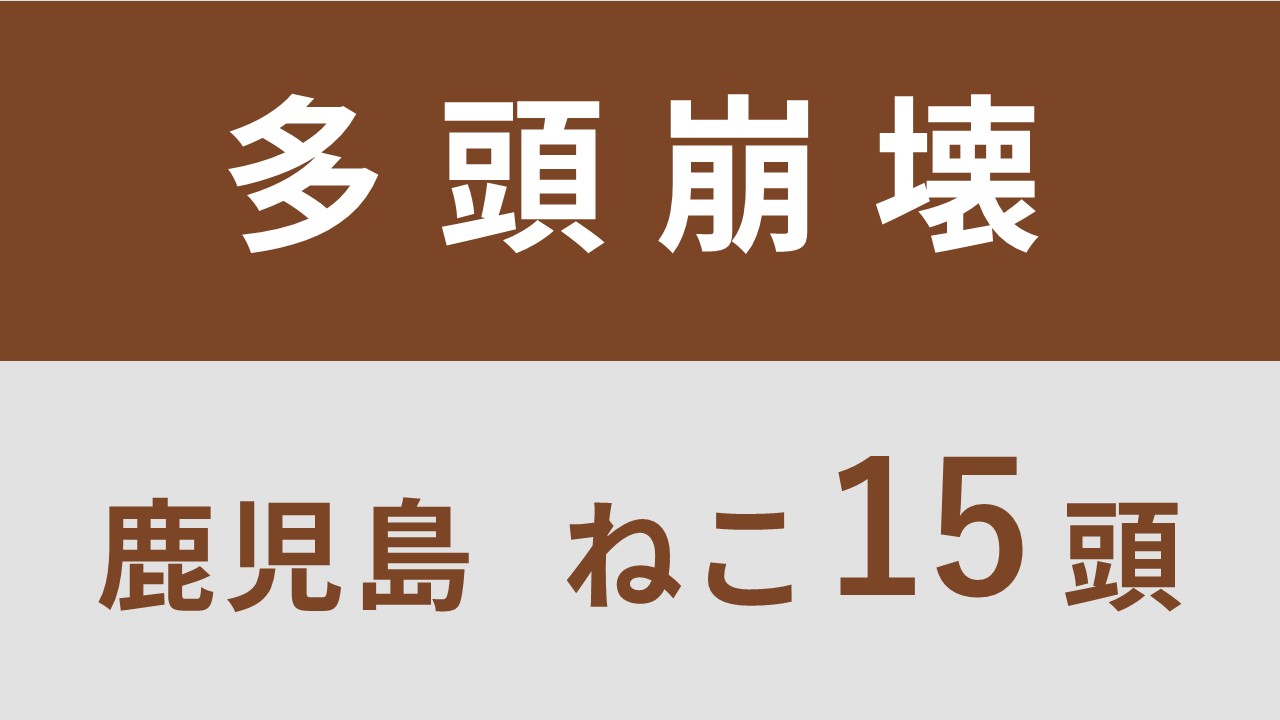7_奈良県御所市多頭飼育救済支援レポート(行政枠)
申請No.7
申請日:2025年4月22日
申請/実施責任者:御所市 環境衛生部 環境政策課
場所:奈良県御所市
居住者:当事者本人(56歳、女、パート)母(83歳、無職)兄(58歳、パート)
居住環境:貸家/一戸建て
生活保護の受給状況:受給していない
多頭飼育現場の猫の総数(うち子猫の頭数):7頭(0頭)
手術日:6月3日、4日
協力病院:おおが動物病院
チケット発行数:7枚
手術頭数:7頭
協働ボランティア:個人ボランティア
申請から不妊手術完了までの経緯(報告書より)
- 数年前から近隣集落から自宅にやってくる野良猫に餌を与えていた。猫は国道を渡りやってくるため、度々交通事故で死亡しており、2年程前に餌を与えていた猫が事故死しているのを発見したのがきっかけで2頭の猫を保護した。
- 野良猫を保護したが飼養経験がなく、猫に関する知識も乏しかったことから不妊手術をしなかった。結果、子猫が生まれ、新たに猫を保護するなどで頭数が増えていった。
- 当事者が職場の同僚で猫の飼養経験が豊富な友人(相談者)に相談した。相談者は、まず不妊手術をすることを勧めたが、当事者は経済的な理由で難色を示した。
- 打開策として、不妊手術をするまでは雌雄を別々に飼うようにアドバイスをする。相談者が当事者宅を訪問すると、猫はケージではなく小型のキャリーケースに1頭ずつ入れられていたため、現状では虐待行為に近い状態であることを説明し改善を促し、ペットケージやトイレなどの飼養環境を整えた。その際に子猫を相談者が引き取っている。しかし、次に訪問すると、ペットケージは屋外に雨がかかる状態で設置されていた。雨がかかることを説明すると、雨風を防ぐためにレジャーシートがかけられ猫が入れられていた。
- また、オス猫同士がケンカをするため、同じケージに入れられない状況で別に小型のケージに入れられていた。
- 相談者から未手術の猫に対しての救済措置ついての問い合わせが当課にあり、多頭飼育が発覚した。
- 申請までに、当事者に対して屋外のレジャーシートががけられたケージは、通常の降雨では雨水が入ることは少ないが、強い雨や風が伴うとケージ内に雨水が入ることを伝える。また、夏季はケージ内が異常な高温になることが考えられ、猫が非常に危険な状態になるため、ケージを室内に入れるよう指導したが、現状では屋内にスペースがなく困難とのことで、相談者に猫を室内飼養できる環境を作るため、片付けなどの作業のお手伝いを依頼し、それを快諾してもらった。
- 当事者は、生活保護受給者ではないが、全ての猫に不妊手術を受けさせる経済的な余裕がない。動物病院までの移動手段も持ち合わせておらず、支援が必要と判断し多頭飼育救済枠の申請を決定。
- 相談者から、もう1人の友人(同僚)と協力して、今後定期的な訪問を実施して、適正な飼養ができるように手助けや助言を行い、当事者もそれに従うことで話がついている。
- チケットを使用して全頭手術済み。全頭当事者宅へ戻り、飼養をしていく。
- 支援前は屋外でペットケージを雨除けのためレジャーシートで覆った状態で清掃も行き届いておらず衛生環境も良いとは言い難い状態だったが、ケージを室内に移動させ、当事者が猫と触れあえる環境に改善することができた。室内で飼養するようになったことで、トイレやケージ内の清掃もこまめにできている。網戸や扇風機の設置など室内の換気ができているため、支援前に比べて臭気は非常に少なくなった。
- 手術時に爪切りをしてもらい、獣医師の報告では、何らかの治療が必要な猫はいないとのこと。
- トイレはグループ+1で4台設置した。運動スペースは分離型で通常はケージの戸は閉めない。外出時などはケージに入れている。キャットタワーを設置する代わりに、ケージの段差を利用して上下運動ができるようにした。運動スペースでは、グループの違う猫同士のケンカもなく共存している。
- 支援後も定期的に当事者宅を訪問して指導などを行っている。
| 手術日 | オス | メス | 耳カットのみ | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 6月3日 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 6月4日 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 計 | 4 | 3 | 0 | 7 |
【現場写真(支援前)】


今回の取り組みを振り返り、改善すべき点や今後の配慮事項(報告書より)
当事者への指導などには、当事者の友人であるボランティアに立ち会ってもらったことで、支援をスムーズに進めることができた。庭のレジャーシートで覆われたペットケージに閉じ込められた猫たちを解放できただけでなく、本来猫好きである当事者が猫と触れあえる環境を作る機会を与えてもらえたことに感謝いたします。
どうぶつ基金スタッフコメント
当事者は、餌やりをしていた野良猫が事故にあい、可哀想だという気持ちからの保護であったと思いますが、不妊手術の必要性の認識がなかったゆえ、多頭飼育崩壊という結果となりました。そして、飼養状況を見る限り、虐待に近い環境であったことは言うまでもありません。友人の方々や行政の力を借りることで飼養環境は改善されましたが、当事者には、引き続き7頭の猫が健やかに穏やかに過ごせるよう、飼い主としての責任を果たしてほしいと思います。