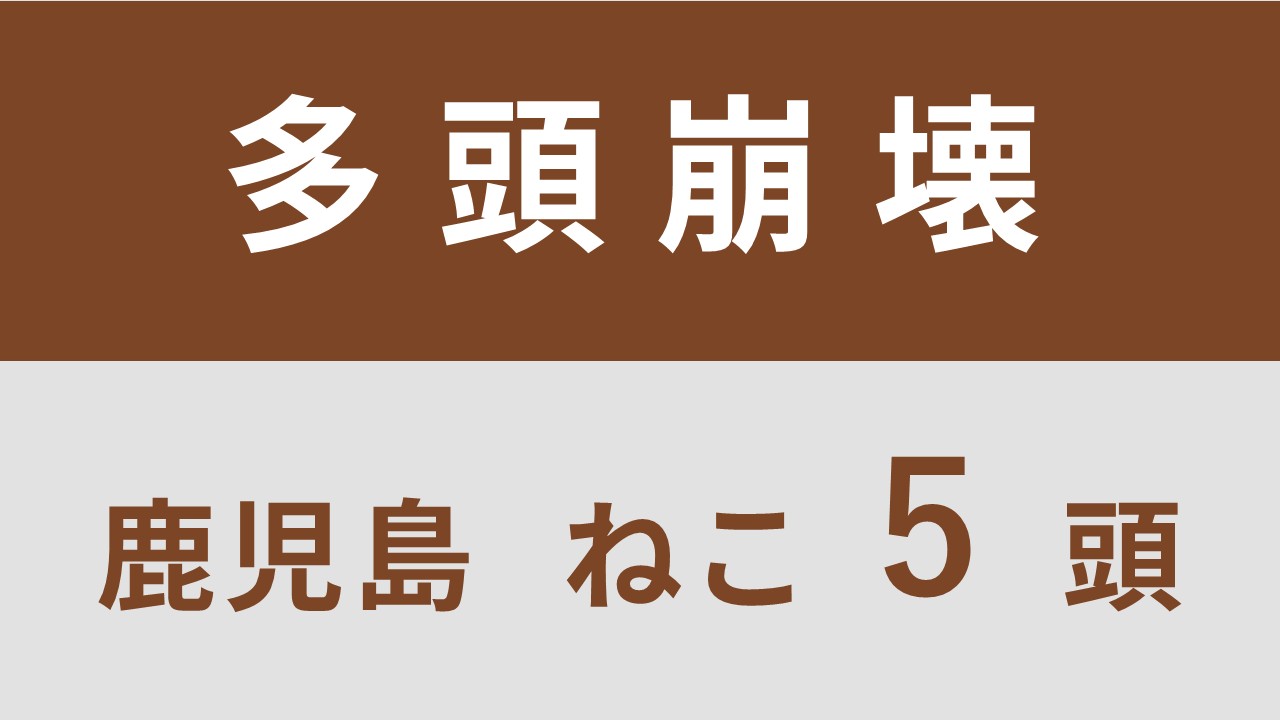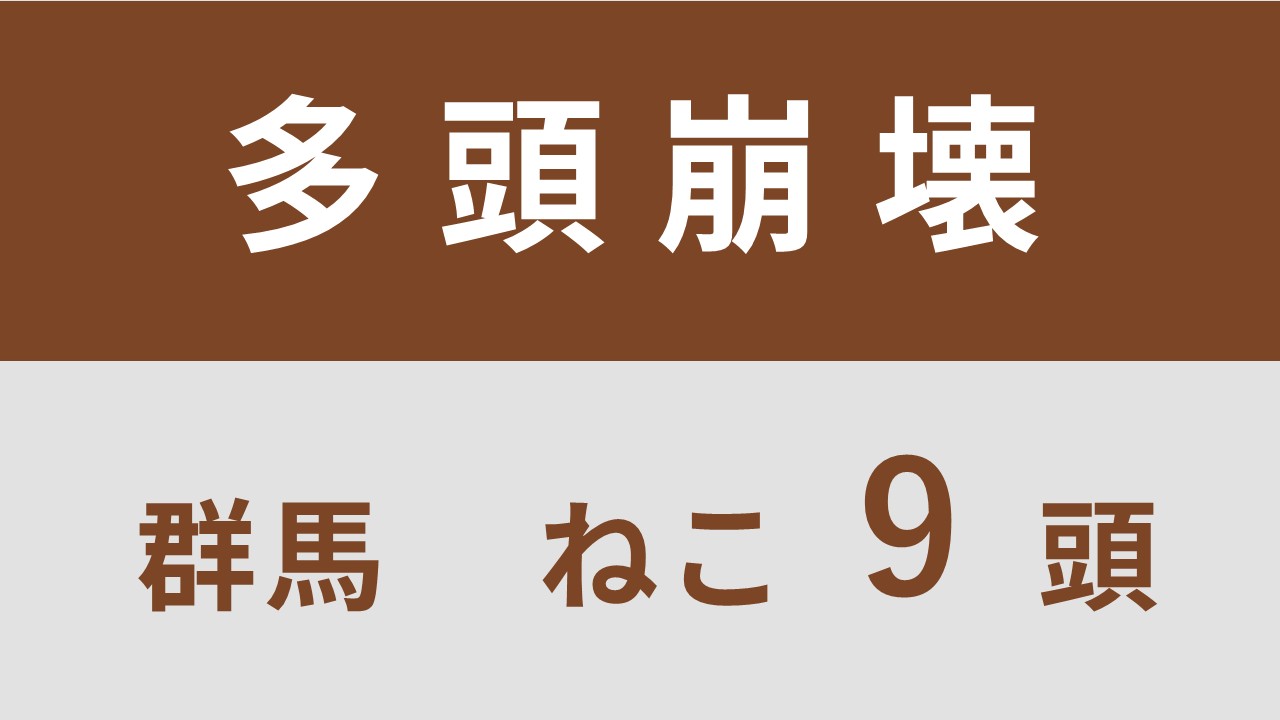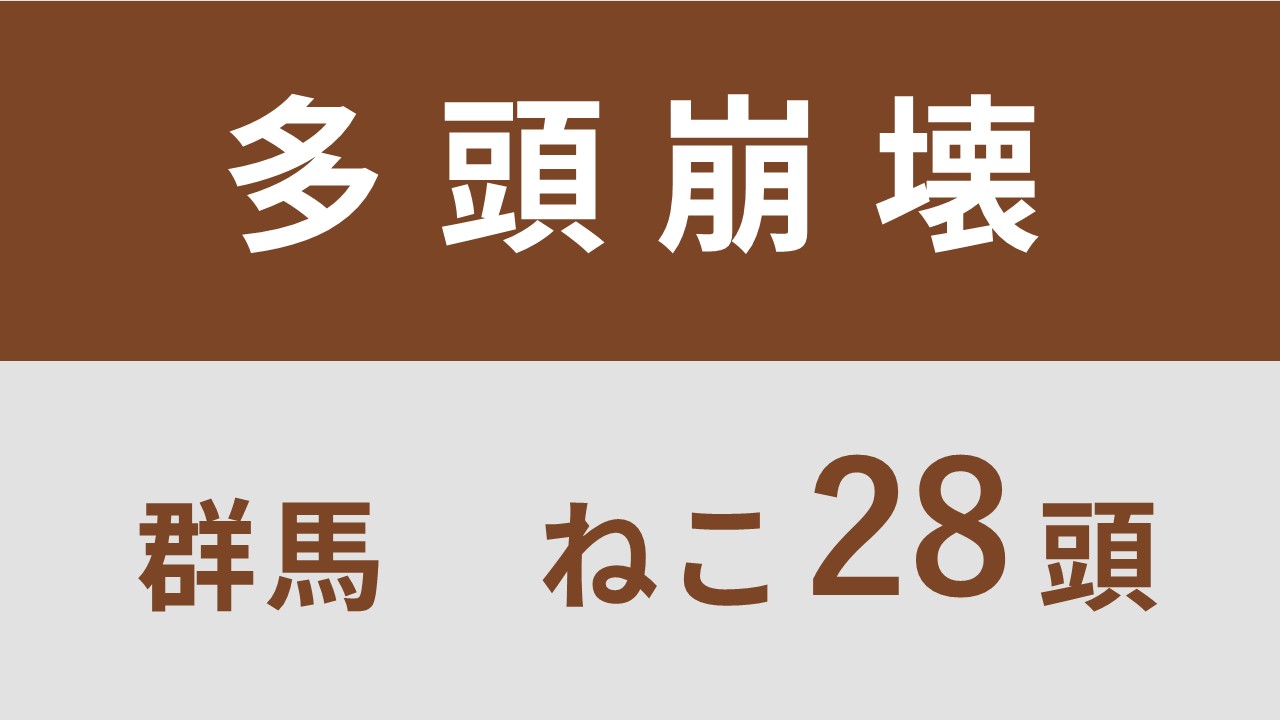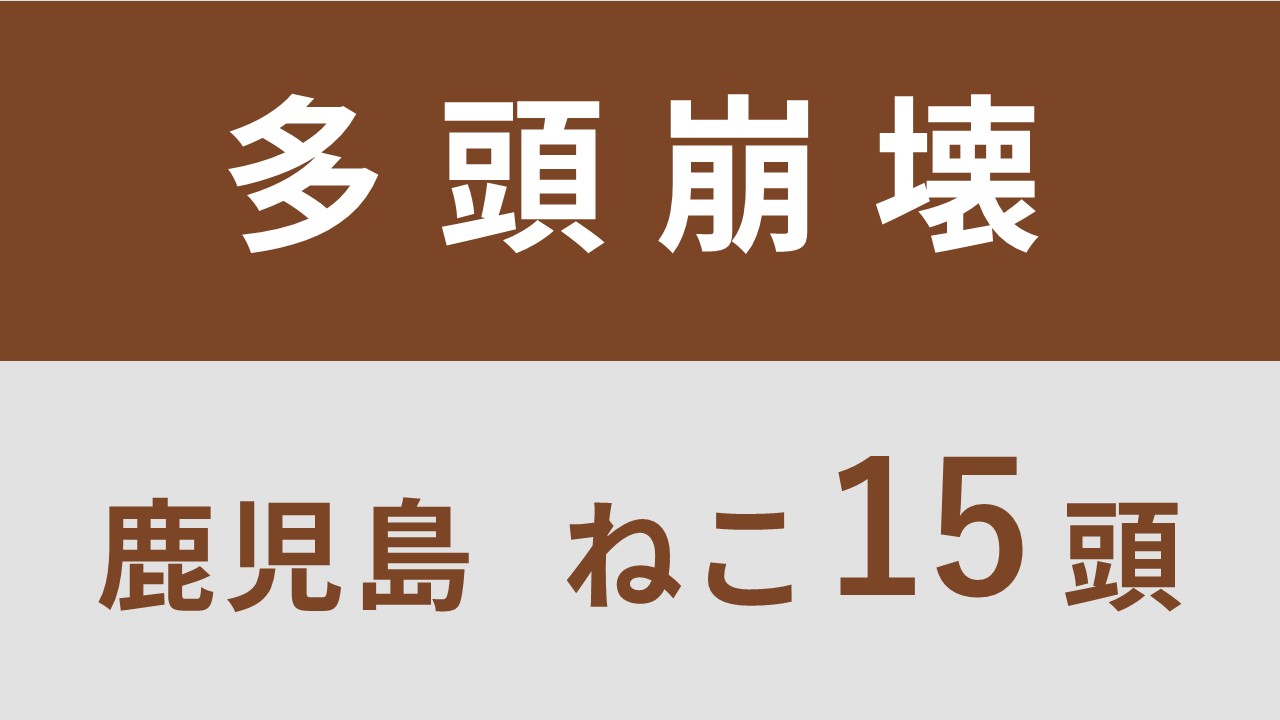59_茨城県下妻市多頭飼育救済支援レポート(行政枠)
申請No.59
申請日:2025年2月28日
申請/実施責任者:下妻市 市民部 環境課
場所:茨城県下妻市
居住者:当事者本人(50歳、男、無職)
居住環境:持ち家/一戸建て
生活保護の受給状況:受給している
多頭飼育現場の猫の総数(うち子猫の頭数):14頭(0頭)
手術日:3月18日
協力病院:茨城さくらねこクリニック
チケット発行数:9枚(手術済5頭を除く9頭分を申請)
手術頭数:9頭
協働ボランティア:なし
申請から不妊手術完了までの経緯(報告書より)
- 3年ほど前、当事者の父が野良猫に餌をやり始めたところ、その猫が自宅に居つくようになった。
- 最初はその1頭だけだったが、別の猫がついてきてその猫にも餌やりをするようになった。徐々に自宅に来る猫が増えていき、猫同士で繁殖したり、どこかで産んだ猫を連れて帰ってくることもあり、1年ほど前には総数が14頭となった。
- その頃から室内飼養を開始するとともに、捕獲できる猫から不妊手術を実施。これまで5頭の不妊手術を実施したが、残り9頭が未手術のままで今後さらに数が増える恐れもある。
- 2024年に当事者の父が他界。それまで父の年金を頼りに生活していた当事者は金銭的に困窮し、2025年より生活保護受給を開始。担当課職員が実地調査で自宅を訪問した際に多数の猫を飼養している状況を発見して、環境課へ相談があり発覚。
- 当事者は中学生の頃から不登校に陥り、20年以上無職で引きこもり状態。日常会話は可能だが、ひらがな、カタカナ、自分の名前程度の漢字を書くことが限界で、障害者手帳の所持はないものの知能面でも周囲の支援が必要と思われる。
- 生活保護を受給していることから残る9頭の早急な手術実施は金銭的に困難であり、当事者単独では実施が見込めない。現状、妊娠中と思われる猫はおらず健康面に問題のある猫も見受けられないが、今後の繁殖と疾病等の防止のためにも、多頭飼育救済の申請により早期に対応することが適切と判断した。
- チケットにより未手術の全9頭の不妊手術が完了し、猫の健康状態も問題ないと思われる。当初、猫のトイレは2個しかなく糞尿であふれていたが7個に増設された。
- 当事者および生活保護担当課職員にて、糞尿がついた座布団の廃棄や猫の居室内の掃除を実施。臭いは完全には消えないが、介入時と比べ大幅に改善している。その後も、生活保護担当課職員が訪問時に清掃実施状況を確認、指導を行っている。
- 猫は当事者が飼養を継続するが、当事者の親族や生活保護担当課職員の協力のもと、徐々に譲渡を進めていく予定である。
| 手術日 | オス | メス | 耳カットのみ | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 3月18日 | 5 | 4 | 0 | 9 |
| 計 | 5 | 4 | 0 | 9 |
【現場写真(支援前)】


今回の取り組みを振り返り、改善すべき点や今後の配慮事項(報告書より)
事案発覚から初回の現場確認後、1か月以内に全頭の手術を完了できたことはよかった。堕胎があったことを考えると、頭数増加の防止に貢献できたと思う。生活保護担当課と連携して複数回現場を訪問し、捕獲の可否、手術当日の流れ、物品の準備や清掃の範囲などを事前に十分検討したことで、捕獲~手術および環境改善においてスムーズに対応できた。
猫の譲渡については当事者を説得しきれていないが、生活保護受給中の14頭飼養は経済的な負担が大きいため、引き続き生活保護担当課と協力して譲渡を促していきたいと考えている。
どうぶつ基金スタッフコメント
生活保護担当課からの情報連携で発覚した事案でしたが、その後の連携と対応がスムーズで早期に不妊手術を完了することができました。今回のように複数の担当課が関わって多角的な支援が行われることで、人と動物、双方の生活環境の改善がしやすくなります。本件でも生活保護担当課による状況確認が継続されており、変化があればすぐに情報が共有され、必要な対応がとられることと思います。
現在、猫の譲渡について当事者は了承していないようですが、何よりもまず繁殖が止まったことで当事者にも今後を考える精神的な余裕が生まれるでしょう。その時がきたら、当事者一人で十分なお世話ができる頭数の見極めや、当事者も納得できる譲渡先探しのサポートを行政にはお願いしたいと思います。