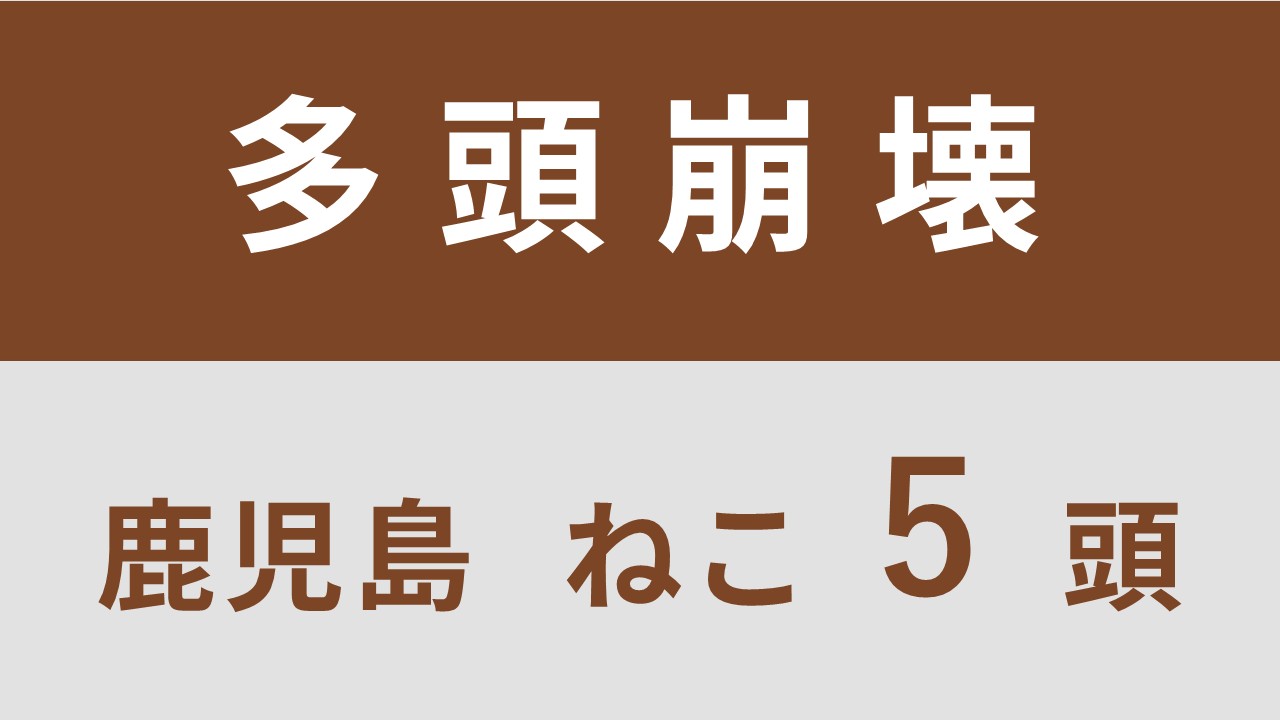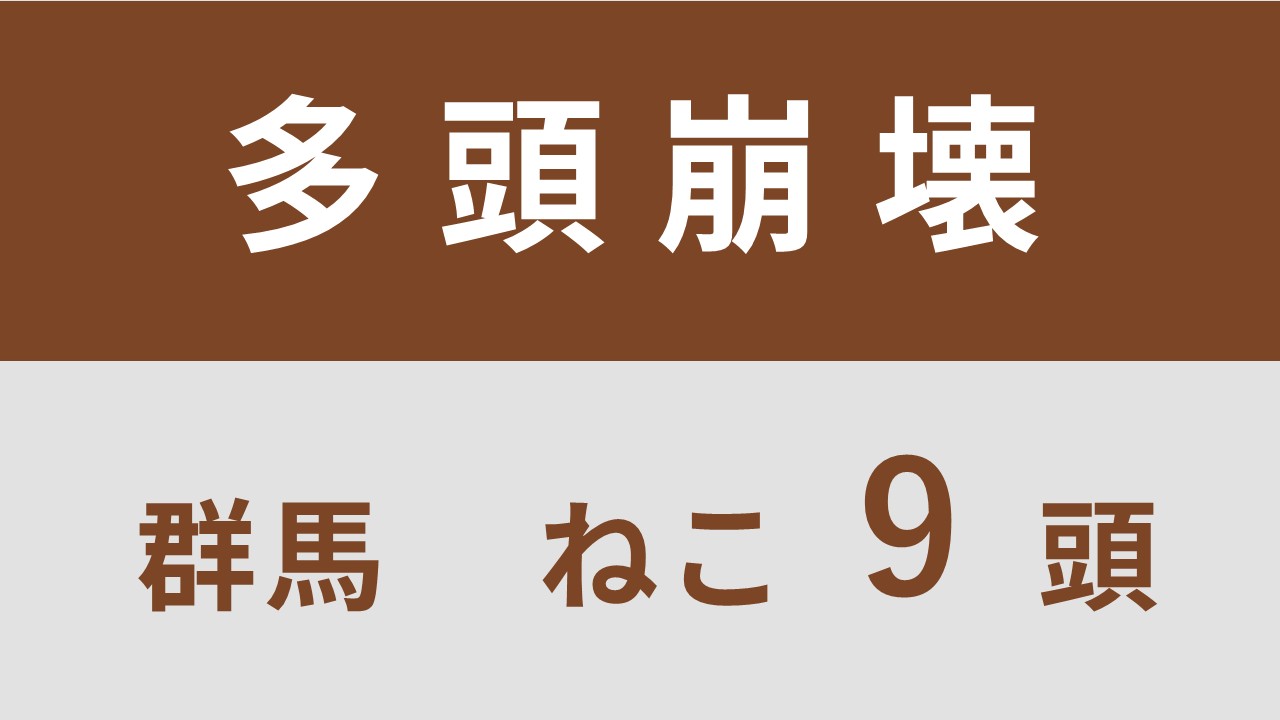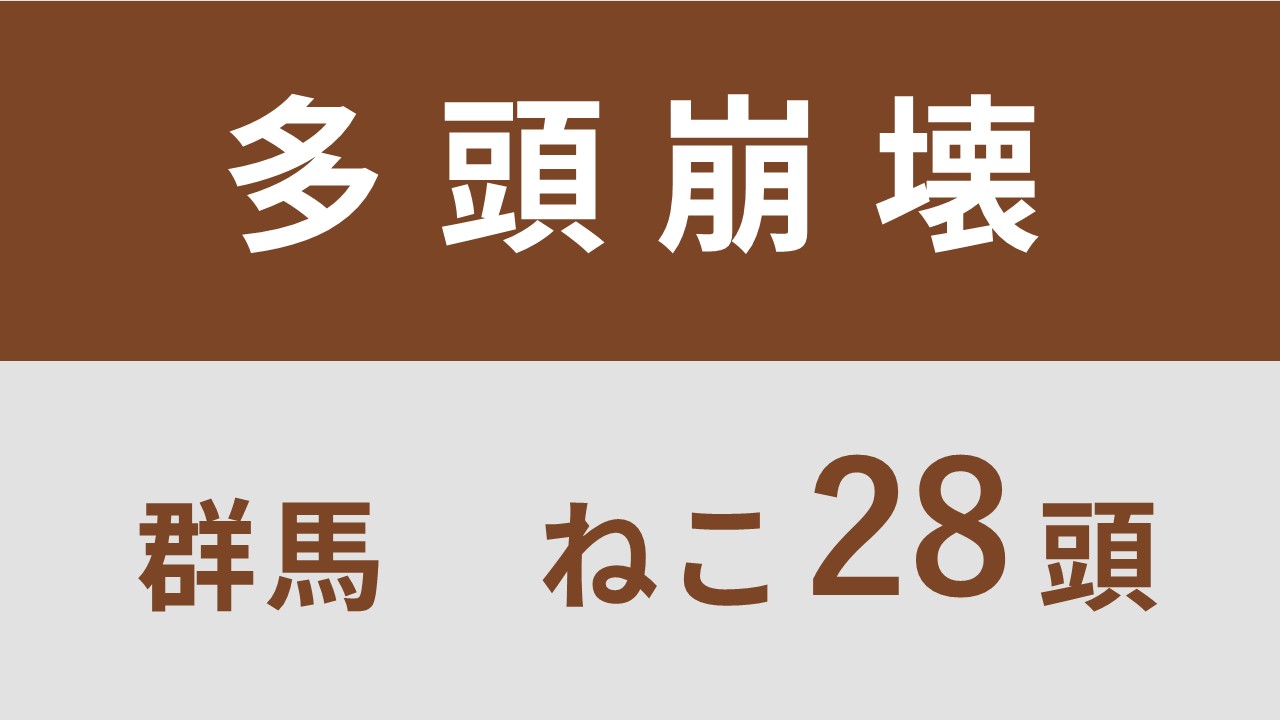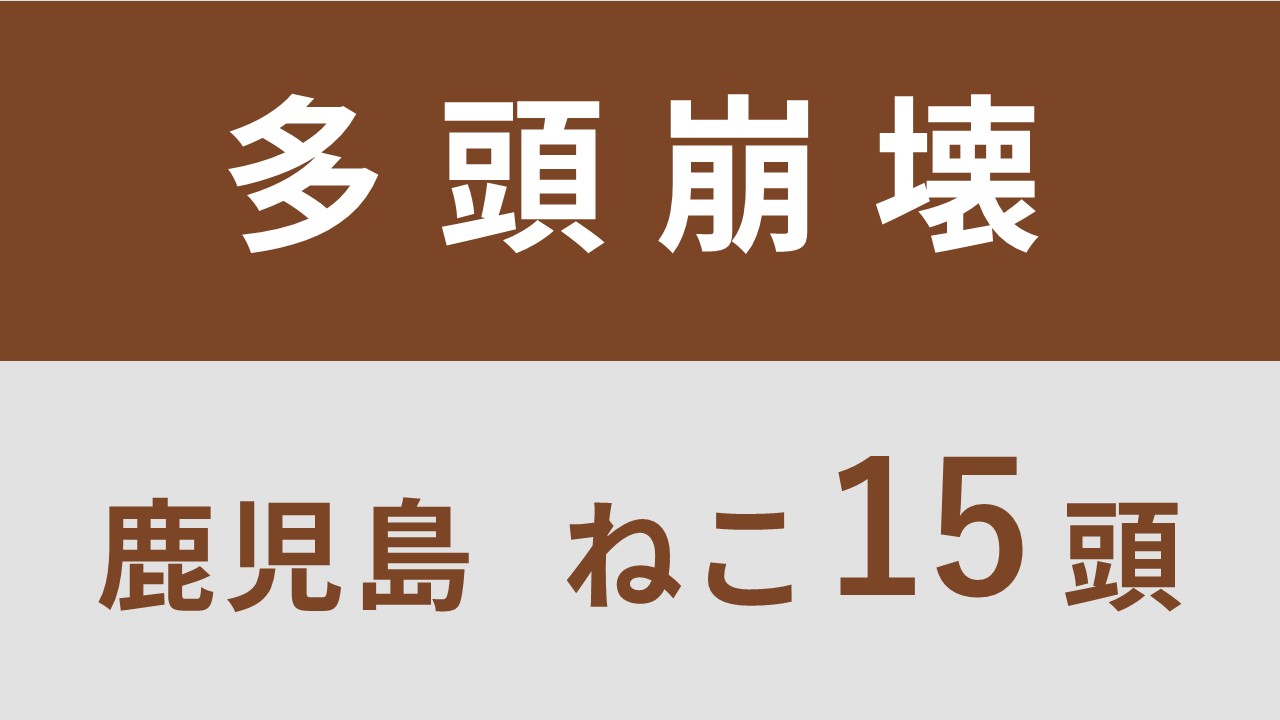41_福岡県那珂川市多頭飼育救済支援レポート(行政枠)
申請No.41
申請日:2024年11月12日
申請/実施責任者:那珂川市 環境課 生活環境担当
場所:福岡県那珂川市
居住者:当事者本人(74歳 男 無職)、同居人(52歳 女 無職)
居住環境:アパート/集合住宅
生活保護の受給状況:受給予定
多頭飼育現場の猫の総数(うち子猫の頭数):42頭(16頭)(35頭で申請するも、最終的に42頭となった)
手術日:12月16日、17日、18日
協力病院:cat spot clinic
チケット発行数:30枚(申請時35頭のうち手術済5頭を除く30頭分を申請)
手術頭数:30頭
協働ボランティア:那珂川ねこネットワーク
申請から不妊手術完了までの経緯(報告書より)
- 4~5年前に友人が飼えなくなったメス猫1頭を引き取った。その後、オスの野良猫1頭を保護して自宅に連れ帰ったことから頭数が増え始めたようである。
- 2022年11月頃、当事者の別居の実娘3名が猫のボランティアグループに相談。実娘らは当事者の生活資金支援を行うほか、猫の不妊手術をボランティアに依頼して行っていた。
- 2024年7月、当事者が居住するアパートのオーナーから「住民から糞尿被害の苦情がきている」と市環境課へ相談が入った。オーナーの話によると、当初は8頭ほどで不妊手術をするように伝えていたが、3年前から急激に増え始めたとのこと。以前は20頭ほどであったが、外猫を拾うなどして現在は40頭ほどになっている様子。オーナーには県筑紫保健所にも相談するように伝えた。
- その後、当事者と当事者の娘2名、アパートのオーナー同伴のうえ、市環境課と県筑紫保健所で立入調査を実施。当事者の娘からは、これ以上の生活支援は困難であり当事者には生活保護を申請させる予定であること、猫に対する資金援助等が困難であるため、同居人の女性には転居してもらい、当事者のもとには猫1頭だけを残して他の猫は譲渡する意向とのこと。
- 手術済み(耳カットあり)の猫は少なく子猫が多い。頭数は40頭弱である。保健所の話では、オスの異臭が漂っているが去勢手術をすれば減少するとのこと。糞尿の散乱はなく清掃はされていた。雌雄を分けて飼育すること、これ以上増えないよう繁殖制限を行うこと、室外へ出さないよう窓は閉めることを指導した。
- 当事者は家賃を滞納するなど生活が困窮している。2024年から始まった福岡県の多頭飼育問題対策補助金制度の利用も検討したが、3つの地区で利用され補助金予算が終了していた。これ以上の猶予がないため、どうぶつ基金の多頭飼育救済支援を申請するに至った。
- 当初、現場の猫は35頭(うち5頭は手術済)としていたが、立入調査後に生まれた6頭の子猫を含めて、実際は42頭であった。生まれた6頭のうち生後2~3週間の3頭についてはボランティアが保護し、適正な時期に不妊手術予定である。
- 保護された子猫3頭と手術済みの5頭を除く34頭が手術対象となり、30頭はチケットを使用、4頭はボランティアの費用負担により全頭の不妊手術が完了した。
- 術後の猫の健康状態に変わりなく、ケージは整備できていないため部屋中を自由に駆け回っている状況。清掃はしているものの、猫の異臭は玄関外まで漂っている。
- 今回の支援で手術済みとなった34頭+もともと手術済みの5頭=39頭は引き続き当事者が飼養しているが、状態が良く人馴れている猫からボランティア団体の譲渡会等で里親を探し、少しずつ頭数を減らしていくことを考えている。
- 今後は、当事者、実娘、行政、ボランティア団体と協議のうえ誓約書を取り交わし、定期的に当事者宅を訪問して適正な飼養等指導を行っていく。また、アパートのオーナーが代わり、新オーナーのもと住み続けられるかを見守っていく必要もある。当事者については、地域包括センターや生活福祉課等と連携して見守っていく予定である。
| 手術日 | オス | メス | 耳カットのみ | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 12月16日 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 12月17日 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 12月18日 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 計 | 15 | 15 | 0 | 30 |


今回の取り組みを振り返り、改善すべき点や今後の配慮事項(報告書より)
どうぶつ基金に支援いただいたことで、さらなる頭数の増加(繁殖)や地域周辺への状況悪化を防ぐことができました。今回の事案を通して、日頃から高齢者に接している介護職員や福祉関係機関との連携協力が重要であることが認識させられた。30頭以上の猫たちを、協力病院、行政、ボランティアグループと連携しての協働作業により、短期間でスムーズに遂行することができた。
どうぶつ基金スタッフコメント
多頭飼育崩壊の不妊手術もTNRと同じく「すぐやる・全部やる」が大切です。数頭ずつ手術をしている間に他の猫が妊娠・出産し、猫の繁殖力に追い付きません。行政の報告では、2022年11月頃に発覚した時点で何頭いたかは不明ですが、この時に全頭を速やかに手術できていれば、40頭超という状況になることは避けられたのではないかと思います。
特に、2022年度はどうぶつ基金が福岡県でTNR地域集中プロジェクトを実施中で、那珂川市も登録行政であったことから本支援制度を利用することも可能でした。やはり、多頭飼育者に関する情報をいち早くキャッチするための体制づくりが求められます。
本件は、幼齢の子猫3頭はボランティアに保護され、手術が必要だった34頭は全頭手術済みとなりました。現在のアパートで継続して居住できるかまだ不透明な部分はありますが、離れて暮らしておられるとはいえ実娘の方の協力と、行政・ボランティアの見守りがあることは明るい材料だと思います。1頭でも多く幸せに向けて送り出せるよう、譲渡先探しを決してあきらめないでください。譲渡先が見つからずとも飼養環境をさらに改善し、最後の1頭を看取るまで愛情をもってお世話を続けることは言うまでもありません。